ブログ
関西万博は引き算で大成功
皆さんはもう関西万博に行かれたでしょうか。私は通期パスを購入して数回足を運び、ある程度コツをつかめてきました。しかし、開幕当初は全くパビリオンに入れず、苦い思いを何度もしたものです。その原因は、独特で複雑な入館方法にありました。
パビリオン入館方法の実態
万博では「並べば入れる」と思いきや、基本はアプリを通じた予約制です。正しい方法は大きく3つに分かれます。
-
事前予約:公式アプリから日時を指定して予約する方法。人気パビリオンは即満席になることも多い。
-
当日予約:入場後にアプリから当日枠を予約。時間やタイミング次第でチャンスあり。
-
予約不要(並ぶ方式):一部パビリオンは並べば入館可能。ただし待ち時間は数時間に及ぶ場合もある。
公式アプリでは入場券購入から予約管理まで一括で行えますが、これが初見には分かりづらく、まさに“初見殺し”。さらにデジタルに不慣れな高齢者にとってはハードルが高く、人気パビリオン前で何時間も並んで疲れ果てて帰る光景も珍しくありません。
会場の混雑と攻略法
4月に訪れた際も多くの人で賑わっていましたが、その後さらに来場者は増え、ピークが見えないまま残り1か月半を切りました。一見すると「情報弱者切り捨て」の万博ですが、少し慣れれば目当てのパビリオンに入れるようになり、満足度も高いと感じています。実際に体験したものの中で、印象的だったパビリオンを挙げると次の通りです。
おすすめパビリオン
-
フランス館
ルイビトンなど高級ブランドと、ロダン彫刻の展示など文化伝統を圧巻のビジュアルで見られる。 -
日本館
着眼点は地味だが、古来からあるもの、その辺にあるもの、着目すらしていなかったものにスポットライトを浴びせ、未来への可能性を提示している。空間の使い方にセンスを感じた。 -
いのちの未来
アンドロイドに記憶と感情を移して生き続けられる未来を追体験出来る。途中にあったショートムービーでは咽び泣く来場者が多数。いのちのかたちを考えさせられた。 - ガンダム
宇宙エレベータで成層圏を超えて小宇宙旅行。するとジオン軍のモビルスーツが暴れ出し、ガンダムが助けてくれる・・・という男の子がワクワクする世界観。屋外の実寸大ガンダムの展示も相まって注目度と満足度が高い。ガンダムに翼が生えるのは知らなかった。 -
テックワールド
大人の事情で国の名前は言えないけれど、台湾だってことはみんな知ってる。半導体チップの可能性を提示する最も現代的なパビリオン。スマートウォッチを装着し、どの展示で一番感動したか可視化してくれる。 -
クウェート館
子どもが喜ぶ砂遊びが出来る展示と、結構急な滑り台が特徴。意外とすんなり入れて楽しめる。
あまりおすすめできないパビリオン
-
大阪公立大学館
母校なので入ったが、つまらなかった。 -
オーストラリア館
自然が売りのオーストラリア大陸。本当に本物のコアラやカンガルーがいればまだしも、全て作り物で面白くもなんともない。本物の動物の糞の臭いを再現するブースがあり、不快だった。 -
アニマ館
芸術家が作った光と音と振動のアート作品。立ちながら寝るぐらいつまらなかった。小学生が遠足で入ったら喜ぶと思う。 -
コモンABCDE
暑いのでエアコンで涼みたい人と、とにかく並ばずに沢山の国のスタンプを捺したい人向け。アフリカの雑多な小国や、オセアニアの島国は大体木彫りの置きものと民族衣装を飾っている。それだけ。 -
サウジアラビア館
金持ちな国って感じ。ちょっと涼しい。デーツのおやつが売ってるので欲しい人は買いに行ってもいいかも。レストランは数時間待てば入れる。
もちろん評価は個人差がありますが、完成度の高い展示に出会えたときの体験は格別でした。
「引き算」で見えた主催者の狙い
タイトルに書いた「引き算で大成功」という表現は、誰を大切にしたかという観点での“引き算”です。今回の万博は、スマホでの決済・予約・情報収集が必須であり、50年前の万博を知る世代をある意味で置き去りにしました。つまり「現代のデジタル環境を使いこなせる層」を対象に絞り込んだのです。
結果として、高齢者でもスマホを駆使して楽しめた人は多く、QRコードやアプリ予約を使いこなすきっかけになった面もあります。一方で、並ぶだけで何もできなかった人は「しんどかった」「楽しくなかった」と周囲に話すでしょうが、その発信力はSNSで拡散されるわけでもなく限定的です。逆に、攻略できた人々はSNSで体験を自慢し、情報を共有し合い、「選ばれた感覚」を楽しんでいるのです。
結論:全員向けではないからこそ成功
全ての世代に受け入れられる万博ではありません。しかし、あえて引き算をしたことで、デジタル世代にとっては最高の体験を得られる場となりました。私はこの「引き算の万博」こそ、結果的に大成功だと考えています。



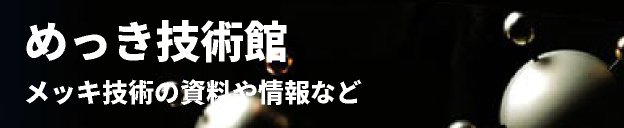
コメントを残す