ブログ
30年前ボーイスカウト奈良第16団に所属してました
幼い頃、あまりにも手のかかる子どもだった私を見かねた母が、ある日ふと思いついたそうです。
「この子には規律が必要だ」と——。
そんなわけで、カトリック幼稚園に通っていた数人の友達と一緒に、私はボーイスカウトに入団することになりました。奈良16団という団体で、在籍期間は幼稚園の年長さんから小学校3〜4年生ごろまでだったと記憶しています。一度辞めると二度と再入団できないというルールがあるため、あの経験は今も唯一無二の思い出となっています。
振り返れば、軍隊式の規律と自然の中でのサバイバル訓練を通して、あの時間が自分の性格や価値観の一部を形作ったのだと感じています。
子ども心に感じた「目的がわからない」しんどさ
ボーイスカウトの活動は、子どもたちだけでなく、その保護者も隊員として同行するスタイルが基本でした。奈良市・中登美ケ丘にあった団地の中心にある奈良16団の拠点に集合し、そこからどこに行くとも知らされず、ひたすら歩く——そんな日が意外と多くありました。
たとえば、ある日。奈良ドリームランドでプール遊びをしたあと、「じゃあ、歩いて帰りましょう」と指示が下ります。今のGoogleマップで確認すると、徒歩で約2時間の距離。当時の子どもの足では3時間近くかかったのではないでしょうか。すでにプールで体力を使い切っている中での長距離行軍は、今思えばかなりハードな大人たちだったと思います(笑)。でも、誰ひとり途中で倒れたり、リタイアしたりしなかったのは、鍛えられていた証拠かもしれません。
中には、ただ「目的地を告げられず歩き続けるだけ」という日もありました。山道やハイキングコースではなく、大通りの歩道をひたすら歩くだけ。精神修行のような、黙々とした行軍でした。大人たちも徹底していて、どこへ向かっているのか最後まで教えてくれません。帰り道だと気づいたときの、あの絶望感と疲労感は今でも覚えています。
手旗信号という鬼門
毎年恒例の泊まりがけイベントもいくつかありました。私はホームシックとは無縁の子どもだったので、参加できるものはすべて親に頼んで行かせてもらっていました。全国から団員が集まる、海辺のキャンプ施設での大規模合宿もありました。真夜中に起こされて点呼を取られるという「軍隊ごっこ」さながらの体験も、今となっては貴重な思い出です(点呼のときの記憶はないのですが…)。
その中でも忘れられないのが「手旗信号大会」です。赤と白の旗を使って、カタカナを2つの動作で表現し、遠く離れた相手と意思疎通を図る通信手段。速さと正確さを競う大会だったのですが、私はこの手旗信号が本当に苦手でした。普段使わない・今後も使わないであろうことを覚えるのが、当時の私にはとても難しく感じたのです。
初めての野宿とサバイバル
夏のキャンプでは、天気が良かったため、テントを立てずに屋根だけ張り、ビニールシートの上に寝袋を敷いてそのまま寝ました。
「え、これで寝るの…?」と最初は戸惑いましたが、意外と寝られるものです。
トイレはまず地面に穴を掘って作るところから始まり、テントの周りには雨水の侵入を防ぐための溝も掘らされます。夕食は定番のカレーライス。水が貴重なので、食器洗いも工夫が必要でした。まずはお皿を舐めて綺麗にし、水でさっとすすいでから、最後に泡をつけたスポンジで軽くこするだけ。
「ないものは自分たちで作る」 「足りないものは大切に使う」 「道具がなければ工夫する」
このとき培われた“工夫する心”は、今でも私の中で生きています。だから大学生のころは、旅先で野宿することに何の抵抗もなく、宿代を浮かせることを当たり前のようにしていました。
鼓笛隊?ああ、奈良16団ね
社会人になってから、ボーイスカウト活動を今も続けている方と出会いました。出身地が同じ奈良だったことから、私が「奈良16団にいた」と言うと、「ああ、鼓笛隊やん」と即座に返されました。
そう、奈良16団はちょっと変わった団で、小学2年生でビーバーからカブスカウトに上がると、毎週水曜の夜に小太鼓(スネアドラム)の練習が始まるんです。ドラムスティックを買ってもらい、ひたすら連打の練習。マーチングパレードのために練習を重ね、地域のイベントにも多数参加していました。私自身は退団が早かったので、あまり上達しませんでしたが…。
この友人いわく、奈良16団は大人から見ても“かなり変わり種”の団だったそうです。でも、それこそがボーイスカウトの良さ。団によって色があり、正解もひとつじゃないのだと教えてくれました。
募金活動
少年少女が募金活動を呼びかけるのはグッと心をつかみます。我々の行動の中に募金活動も良く含まれていました。ある日、24時間テレビのチャリティー募金で、もしかしたら募金活動の様子が放映されるかもしれないということで、大声を張り上げて行き交う人に募金協力をお願いしましたが、一切放映されませんでした。
放映されなかったら募金活動をしないのかと心に問えば、そんなの関係ねえの一点張りをしますが、あの時から24時間テレビを1時間でも見たら負けだと思い見ないようにしています。
一人ずつ辞めていく仲間たち
小学2年生になると活動内容も本格化し、次第に友達がひとり、またひとりと辞めていきました。母に「続けたい?」と聞かれたとき、私は正直「行軍訓練だけは嫌だ」と思っていましたが、それ以上にアウトドア活動が楽しかったので、やめたくありませんでした。
気がつけば、同じ学校の子は誰もいなくなり、自分ひとりだけが週末に車で送り迎えされて参加する状態。普段から一緒に遊ぶことのない仲間との活動は、次第に寂しさを感じるようになっていきました。
やがて、土曜日の朝に「行きたくない」と言うようになり、ついに母との話し合いで退団を決意しました。ルール上、再入団は不可能。私は、奈良16団を「永久退団」することになりました。
今も残る、あの場所と記憶
あの頃の拠点の裏には小さな山があり、そこに入ってキャンプを張ったりもしていました。今では宅地造成が進み、イオンやマンション、奈良学園などが建ち並んでいます。
それでも、あの拠点は今も残っていて、何年かに一度その前を通るたび、「まだやってるんやな」と、懐かしさと少しの誇らしさを胸に感じます。
私を育てた、日本ボーイスカウト奈良連盟第16団。
鼓笛隊で、行軍で、野宿で、鍛えられたあの記憶は、今も確かに心のどこかで、静かに息づいています。



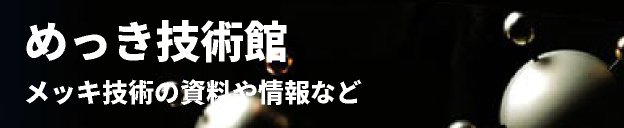
コメントを残す