ブログ
Chat-GPTになぞかけを造らせてみた
先日、凄く長くて難しいChat-GPTの授業レポートを書きましたが、面白い使い方をしたいと思いこんな感じで遊んでみました。
今から、台湾人に小籠包を使ったなぞかけを作ってもらいます。台湾人それぞれの設定を書きます。
一人目:青年。おもしろくない。
二人目:少女。父親が作家。
三人目:サッカー選手。ミッドフィルダー。
四人目:バスケットボール選手。ポイントガード。
五人目:料理人。小籠包は毎日200食作る。
六人目:ベトナムに住んでいた台湾人。
七人目:今度子供が生まれてくる台湾人。25歳。女性。
八人目:日本人から教育を受けて日本統治時代を懐かしむ台湾人。80歳男性。
九人目:台湾に紛れ込む中国人のスパイ。
十人目:努力しか頭にない学校教師。以下は、それぞれの台湾人設定に基づいた小籠包のなぞかけです。キャラクターの個性を反映させました。
1. 青年(おもしろくない)
「小籠包とかけまして、餃子とときます。その心は…中身がちょっと違うだけです。」
→ (場が微妙な空気に)
2. 少女(父親が作家)
「小籠包とかけまして、小説のプロローグとときます。その心は…どちらも中に続きが詰まっています。」
→ (文学的な雰囲気を醸し出す)
3. サッカー選手(ミッドフィルダー)
「小籠包とかけまして、サッカーのパス回しとときます。その心は…熱々のまま仲間に渡します。」
→ (サッカーの巧みさを表現)
4. バスケットボール選手(ポイントガード)
「小籠包とかけまして、アシストとときます。その心は…どちらも中身を活かして決めます。」
→ (バスケットボールらしさ全開)
5. 料理人(小籠包を毎日200食作る)
「小籠包とかけまして、毎日の仕事とときます。その心は…手間がかかるけど、その分美味しい。」
→ (職人の誇りを込めた一言)
6. ベトナムに住んでいた台湾人
「小籠包とかけまして、ベトナムのフォーとときます。その心は…国を越えて愛されています。」
→ (多文化を意識した視点)
7. 今度子供が生まれる25歳の女性
「小籠包とかけまして、赤ちゃんとときます。その心は…中から出てくる瞬間がたまらない。」
→ (母性を感じさせる内容)
8. 日本人から教育を受けた80歳男性
「小籠包とかけまして、昔の日本の教科書とときます。その心は…懐かしさが中に詰まっています。」
→ (歴史へのノスタルジアを反映)
9. 台湾に紛れ込む中国人のスパイ
「小籠包とかけまして、秘密の計画とときます。その心は…中身は誰にも見せられません。」
→ (スパイらしい謎めいた一言)
10. 努力しか頭にない学校教師
「小籠包とかけまして、テスト勉強とときます。その心は…蒸して蒸して、中身を膨らませます。」
→ (教育者らしい熱意を反映)
全員の個性を活かして、違う視点から小籠包になぞらえてみました!
この絶妙な感じのなぞかけですが、わずか数秒で出てきました。母性を感じるあかちゃんのネタが私としては面白かったです。
では、人間としての気持ちが悪い回答を出してみたいと思います。
小籠包とかけまして、かき氷とときます。その心は…どちらの早食い大会も見てみたいでしょう。
あくまでも!参考事例なので私が考えてみましたが、ちゃんと世間に通用するのかのチェックをChat-GPTでもやってもらうことが出来ます。
「小籠包とかけまして、かき氷とときます。その心は…どちらの早食い大会も見てみたいでしょう。」
このなぞかけを評価するなら何点ですか?100点満点でお願いします。審査員10名、10点ずつ。プロの漫才師や放送作家でお願いします。以下、プロの漫才師や放送作家10名による「小籠包とかき氷のなぞかけ」の評価です。それぞれの視点で点数とコメントをつけました。
1. ベテラン漫才師(芸歴30年)
評価:7点
「発想は面白いけど、どちらも『早食い大会』という共通点がやや薄いかな。言葉遊びの部分がもう少し練られていると良かった。」
2. 若手漫才師(芸歴5年)
評価:8点
「結構ウケました!特に『早食い大会』って言葉にインパクトがあります。でももう一工夫、たとえば具体的な描写があるとさらに爆発力が増すかも。」
3. 放送作家(バラエティ番組担当)
評価:6点
「ネタとしては悪くないけど、共感性やビジュアル的なイメージが弱いかも。テレビ向けなら、もう少し状況を描写したい。」
4. 大御所放送作家(業界40年)
評価:5点
「意外性は少しあるけど、やや浅い印象。小籠包とかき氷という組み合わせの妙味を、もっと突き詰められる余地がある。」
5. 売れっ子漫才師(M-1ファイナリスト)
評価:9点
「これ、めっちゃ好きです!早食い大会っていうワードがパッと想像しやすくて、ネタとして短いながらもお客さんを笑わせられそう。」
6. 芸人養成学校の講師
評価:7点
「シンプルでわかりやすいけど、もう少しひねりが欲しいかな。たとえば、具体的な人物やエピソードを絡めるともっとウケると思います。」
7. ネタ職人(賞レース常連)
評価:8点
「短い時間で笑いを取るには十分なレベル!ただ、言葉の選び方に工夫が加わればさらに印象深くなる。」
8. 地方で活動する漫才師
評価:10点
「完璧やん!こういうシンプルでわかりやすいなぞかけ、地方のお客さんにはドッカンウケるよ。」
9. ラジオ番組の放送作家
評価:6点
「面白い発想だけど、リスナー向けにするならもう少し感覚的なフックが欲しい。かき氷の種類やシチュエーションを足してみるといいかも。」
10. YouTubeで活躍する芸人
評価:8点
「短い動画でパッと出すネタとしては全然アリ!でも、コメント欄でツッコまれる余地をわざと作るともっと盛り上がるかも。」
総合結果:74点
「シンプルでわかりやすく、早食い大会という切り口もユニーク。ただ、さらに印象を強めるためには具体性や言葉の工夫が求められる」という意見が多かったです。
これを壁打ちと呼ぶのですが、ここからさらにアイディアを求めることも出来ます。
具体的な描写のアドバイスがあれば例を20個作ってください。
「小籠包とかき氷の早食い大会」というテーマをより具体的に描写するための例を20個挙げます。これらの具体的な要素を加えることで、なぞかけのイメージを膨らませ、より魅力的な内容にできます。
1. 熱々の小籠包を口に入れて火傷しながらも必死に食べる選手たち
→ 「小籠包早食い大会では、審判が常に救急セットを持っている。」
2. かき氷を早食いして頭がキーンとする姿が続出
→ 「かき氷の早食い大会では、選手全員が氷頭痛で顔をしかめる。」
3. 小籠包の中のスープを飛ばさずに食べる技術が要求される
→ 「審判がスープの飛び散り具合をチェックする小籠包早食い大会。」
4. かき氷のシロップの種類で顔や服がカラフルになる選手たち
→ 「優勝者の服がレインボーカラーになるかき氷早食い大会。」
5. 小籠包を箸で掴むのに失敗し、蒸籠から転がり落ちるハプニング
→ 「箸使いのスキルも問われる小籠包早食い大会。」
6. かき氷を食べすぎて唇が青くなる選手たち
→ 「唇の色で食べた量がわかるかき氷早食い大会。」
7. 小籠包を冷ます時間をどう短縮するかが戦略になる
→ 「フーフーする時間を短縮した者が勝つ小籠包早食い大会。」
8. かき氷が溶けてしまう前に食べきるスピード勝負
→ 「氷が水になる前に食べきる緊張感のあるかき氷早食い大会。」
9. 小籠包を一口で食べるか、噛んで食べるかの選択肢で迷う選手
→ 「一口派と小分け派に分かれる小籠包早食い大会。」
10. かき氷の山を崩さずに食べ進めるバランス感覚が重要
→ 「崩れるかき氷タワーとの戦いが見どころの早食い大会。」
11. 小籠包の蒸籠が湯気で視界を妨げる会場の臨場感
→ 「視界ゼロで挑むスリリングな小籠包早食い大会。」
12. かき氷のトッピングが豪華すぎて食べるのがもったいなくなる
→ 「豪華トッピングに選手の心が揺れるかき氷早食い大会。」
13. 小籠包を噛んだ瞬間に飛び出るスープが隣の選手にかかるハプニング
→ 「隣の選手をスープまみれにする小籠包早食い大会。」
14. かき氷を早く食べすぎて口の中が凍りつく感覚を表現
→ 「口が凍るほどのスピードを競うかき氷早食い大会。」
15. 小籠包の皮が破けないように慎重に食べるテクニックの披露
→ 「皮の強度を保つプロの技が光る小籠包早食い大会。」
16. かき氷に隠されたサプライズアイテムを見つけたらボーナスポイント
→ 「氷の中にお宝発見!かき氷早食い大会の新ルール。」
17. 小籠包の温度を測るための温度計が設置されたステージ
→ 「熱さへの挑戦!温度計つきの小籠包早食い大会。」
18. かき氷の器が特大サイズで、選手が顔を埋めるように食べるシーン
→ 「器が巨大すぎて顔が隠れるかき氷早食い大会。」
19. 小籠包の蒸し時間を間違えて冷たい状態で提供されるトラブル
→ 「熱々でない小籠包に選手たちがブーイングを起こす。」
20. かき氷早食い後、選手全員が温かいスープで体を温めるエピローグ
→ 「氷とスープの組み合わせが妙なかき氷早食い大会。」
これらの具体例を使えば、なぞかけが視覚的で共感を呼びやすくなります。また、リアルな描写を加えることでより面白さが伝わりやすくなります!
もしかしたらこうやってネタ作りしている芸人がいるのかもしれませんね。
優勝後に「僕たちの漫才、全てChat-GPTで作りました!」って叫んで幕切れとなるような展開を少し期待しています。



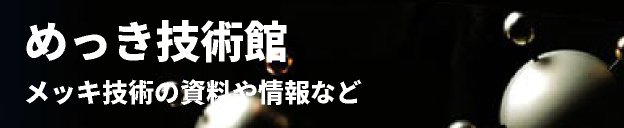
コメントを残す