二度目にして、ようやくこの映画に捕まった
私が『かぐや姫の物語』を観たのは、今回が二回目だった。
公開当時、高畑勲監督作品として大きく話題になっていた一方で、「面白くない」「よく分からない」という感想も多く目にした。その空気に引っ張られ、私はこの作品を後回しにしていた。
一度目に観たとき、確かに違和感はあった。知っている竹取物語とは違う。しかしそれ以上に印象に残ったのは、物語を外側から眺めている感覚がほとんどなかったことだ。まるで第三者として観る映画ではなく、かぐや姫の視界をそのまま借りて世界を体験しているような感覚。俯瞰ではなく没入、物語というより体験に近かった。
ただ、そのときは「変わった映画だな」という印象で終わった。
二回目の今回は違った。年齢を重ね、自分自身の選択や後悔、諦めをそれなりに積み上げた状態で観ると、この映画は一気に牙を剥いてきた。理解した、というより、捕まったと言った方が正しい。
この作品がまず評価されるべき理由
『かぐや姫の物語』は、映像表現の独自性や作画技法で語られがちだ。しかしこの作品が名作である理由は、もっと根源的なところにある。
この映画は、人間が「生きる」という行為を、徹底的に肯定も否定もしない。ただ、その構造を冷静に、残酷なほど正確に描いている。
幸福とは何か。自由とは何か。選ぶとはどういうことか。そして、選べなかった人生とは何なのか。その問いを、観客に委ねるのではなく、感情と身体感覚で突きつけてくる。
だから観終わったあと、スッキリしない。答えが出ない。だがその不快さこそが、この映画が娯楽で終わらない理由だ。
かぐや姫と貴公子たち──愛が経済に変換される瞬間
かぐや姫に群がる貴公子たちを見ているうちに、私は現代のある構図を思い出していた。
水商売におけるキャバ嬢と、金を持つ男性の関係だ。
キャバ嬢は、店というシステムの中で、客からどれだけ金と時間を引き出せるかによって価値が決まる。疑似恋愛を演じ、相手を特別な存在だと思わせ、つなぎ止める。一方で男性側は、その疑似恋愛を本物にしたいと願う。
性欲、見栄、承認欲求。普段接点を持てない若い女性と関係を持っている自分を誇示したいという欲望。LINEでの頻繁なやり取りが情に変わり、疑似が本気へとすり替わっていく。
かぐや姫もまた、男たちに「愛を証明してみせろ」と要求する。金、時間、労力、時には命がかかるものを差し出せと迫る。最初から不可能だと分かっていながら、男たちは性欲と名誉欲のために、愛をリソースへと変換し、嘘で塗り固める。
この構造は、水商売と驚くほど似ている。
ただし、決定的に違う点がある。かぐや姫の物語では、経済的主体がかぐや姫自身ではなく翁だった。
翁は「娘のため」と言いながら、自分の価値観と欲望を経済力という形で押し付ける。その結果、すべてが破綻する。皮肉なことに、かぐや姫が心を惹かれたのは、経済力を持たない捨丸だった。
それは、愛を経済に置き換える場面では決して発生しない感情だ。しかし、その愛は社会の中では持続できない。
捨丸と翁──善意と情熱という二つの暴力
翁は善意によってかぐや姫を縛り、捨丸は情熱によって世界を壊そうとする。
翁は「正しさ」を盾にし、捨丸は「愛」を盾にする。しかしどちらも、かぐや姫を主体として扱っていない点で同じだ。
捨丸が妻子を捨ててまでかぐや姫と行こうとする場面は、ロマンチックな救済ではない。それは責任からの逃避であり、他者の人生を切り捨てた上で成立する幻想だ。
この二人の対比によって、物語は「どちらを選べば救われたのか」という安易な希望を最初から否定している。
帝という装置──封建社会の暴力
物語を終焉へと導くのが帝の存在だ。
帝の求愛は、断れば死罪という究極の選択を突きつける。これは恋愛ではなく、支配であり暴力だ。封建社会における女性の人権が、どれほど脆弱だったかを象徴している。
翁ですら、経済力で成り上がったにすぎず、出生というヒエラルキーの前では無力だった。帝の申し出を断れば、すべてを失う未来が見えていた。
現代で言えば、キャバ嬢が引退を考える瞬間に近い。愛を取るか、経済を取るか。自由を取るか、安定を取るか。その先に待っているのは、トロフィーとしての役割だけだ。
月の都──世界神話に共通する理想郷
月の都は、天体としての月ではない。世界神話に共通する理想郷、神域、完成された世界の系譜にある。
ギリシャ神話のエリュシオン、仏教の浄土、ケルト神話のティル・ナ・ノーグ。これらはいずれも苦しみがなく、変化がなく、永遠だ。
そして共通して、人間が長く留まれない場所でもある。
なぜ記憶は消されなければならなかったのか
記憶とは、感情の発生装置だ。記憶がある限り、比較が生まれ、欲望が生まれ、欠乏が生まれる。
かぐや姫が地上で得た記憶は、月の都にとって致命的な異物だ。悲しみを知った者がいれば、悲しみのない世界は成立しない。喜びを知った者がいれば、喜びのない世界は空虚になる。
だから記憶は消される。救済のためではない。世界を維持するためだ。
この映画が私たちに突きつけたもの
この映画は、選択を誤るな、と私に言っている。皆さんにも言っている。
人権や自由は、弱者の武器だ。強者は別の武器を持っている。だからこそ、自分がどこに立っているのかを見誤ってはいけない。
私はこの作品を通して、自分が完全な安らぎよりも、不完全な生を選びたい人間なのだと知らされた。
そのことを隠さずに書くことが、この文章の結びだ。



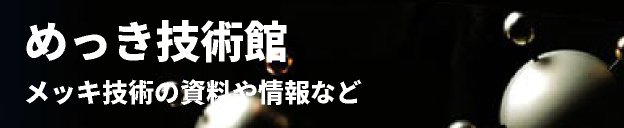
コメントを残す