ブログ
関西万博への複数回来場者の感想
2025年9月27日(土)をもちまして、私の関西万博は幕を閉じました。
この先チケットを取れる見込みはほぼなく、少し寂しい気持ちもありますが、通算8回も訪れたことに大満足しています。
デジタルイノベーションと選別
以前のブログでも触れましたが、今回の万博は「デジタルイノベーションを強制的に起こした」という点で特徴的でした。
入場からパビリオン予約、支払いに至るまで、すべてスマホアプリで完結。スマホが使えない人には一応セーフティーネットは用意されていましたが、正直「不便極まりない」と言わざるを得ません。結果的に、デジタル機器に疎い世代も巻き込んで変化を促した万博だったと思います。
列に並ぶという意識の変化
今回特に感じたのは、日本人の「並ぶ」ことへの意識が大きく変わったという点です。
「2時間並んでも入れるなら入りたい」というマインドが定着し、待つこと自体が当たり前になっていたのです。
1970年の大阪万博では「月の石を見るために5時間待ち」という話が有名ですが、2025年の現代でもアメリカ館に入るために8時間並んだ人もいたそうです。人の忍耐力は時代を超えて健在でした。
9月27日の一日ルート
20万人を超える混雑日でも、事前予約・当日予約・行列入場を駆使すればかなり楽しめました。私のルートは以下の通りです。
-
P&R舞洲A駐車場 → 優先ゲートから入場
-
シンガポール館:入場直後のダッシュで即入館
-
ハンガリー館(ワークショップ):並んで予約枠を確保
-
オマーン館:比較的入りやすい
-
ポルトガル館(レストラン):午前中なら並んで入館可能
-
WASSE特別イベント:「科学マンガサバイバル」限定冊子を入手
-
大屋根リング半周散歩:南側からの水上ショーの眺めが絶景
-
空飛ぶ車試乗:ドローン型で運転手不要、省スペース離発着。あとは安全性のみが課題
-
イタリア館(EATALYレストラン):東京以外では味わえない特別感、1時間並んで正解
-
花火:9月25日から毎日5分間打ち上げ。週末は迫力満点
-
ドローンショー:偶然出会ったが、中央通路は人でごった返し
-
P&R舞洲A駐車場へ戻り:予約なしのシャトルで帰路へ
三種の神器と行列文化
会場では「行列耐えグッズ」が大活躍していました。
-
折りたたみ椅子(アウトドア用の丸椅子)
-
男性でも日傘
-
携帯扇風機
この3つがあれば、炎天下でも何時間でも並べると実証されました。
今後はラーメン屋や新商品の発売日、学校や役所の手続きの列でも、この三種の神器を持った人たちが平気な顔で並ぶ時代になるのではないでしょうか。
待ち時間を楽しむ時代
私自身、以前は「体力と根性で並ぶ派」でしたが、今はスマホで動画やNetflixを見ながら気軽に時間を潰せます。
「待ち時間=苦痛」から「待ち時間=楽しめる」に変わったのも、2025年の万博がもたらした大きな功罪だと思いました。
難点を挙げるなら
正直なところ、万博システムだけは苦言を呈したいと思いました。
入門ゲートでは、システムに繋がりにくい状態が当たり前なのでチケットQRコードは必ずスクリーンショットを撮っておいて、画像としてかざせるようにしてくださいと言われます。実際に混雑し始めた9月以降は、どの時間帯も繋がるまで何分もかかり、場合によっては1時間近く繋がらないこともよくありました。
サーバーの強化ぐらい金掛けてしてくれよと思った次第です。
また、ブラウザでの運用だからこそ不正が多かったとも言われています。入場予約やパビリオンの当日予約など、何度もブラウザから予約ボタンを押して当選・落選を繰り返すのですが、これを自動化出来るツールがネット上ではいくつも紹介されていて、万博運営は不正アクセスに対して厳しい姿勢でアカウントを追放すると言ってはいますが取り締まられていることもなく、こういったツールを使ったアクセスで一般の人はほぼ予約できない状況です。
冒頭で書いたデジタルイノベーションも、所見殺しもいいところで、はっきり言えば何をするにしても知識が足りなければ諦めてしまい、上級者しか利用できないというのは反省すべき点ではないかと思いました。
詰まるところ、不公平感が拭えぬまま終わったなという印象です。
チケットもなんとなく最後の駆け込みで使えなかった人向けに解放したと言っても一日数百人程度。
楽しいと言えるのも、何度も行って攻略法を知ったからこそ言えるし、やはり以前と同様に切り捨てごめんの万博、選ばれし者しか楽しめないというのが今回の万博の反省点かなと思いました。



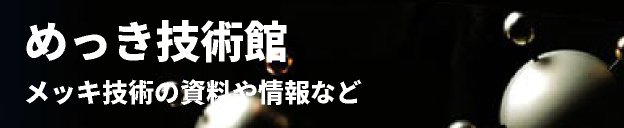
コメントを残す