ブログ
とんこつの匂いが消えた街で、ラーメンはどこへ向かうのか
最近、とんこつラーメンのお店に入っても、昔のような強烈な豚骨臭を感じることが少なくなりました。
特に大阪では顕著で、店の前を歩いても「クサ旨」と言われるほどの獣っぽさが空気に漂うことはほとんどありません。
ところが、先日博多を訪れた際、街中にしっかりと豚骨の香りが存在していました。
「ああ、これだ」と思うと同時に、「大阪ではいつからこの匂いが消えたんだろう」と改めて感じたのです。
では、なぜ大阪からとんこつ臭は消えたのでしょうか。

大阪では「匂いを出せない」構造ができた
大阪のような都市圏では、住宅や商業施設が密集しており、飲食店の排気に対してのクレームリスクが高くなります。
そのため、飲食店には 臭気対策 が求められるようになり、ラーメン店は排気用の脱臭装置を導入するようになりました。
特に「ガツンと炊いたとんこつスープ」は、骨の溶け方や油の酸化による独特の香りが出やすいため、強い匂いを抑えるには「炊き方を変える」必要が出てきます。
結果として、多くの店舗は以下の方向にシフトしました。
-
強く炊かずにクリアなスープへ
-
工場生産のスープや濃縮ベースを使用
-
店内での長時間仕込みを減らす
この変化は、街の空気を変えたと同時に、ラーメンの「匂い」という個性を弱める方向に働きました。
スープの工場生産と均質化
ここ数年、ラーメン業界では スープのOEM(外部委託生産) が急速に広がっています。
-
母体の工場で大量に安定製造
-
店舗では温めて麺に合わせるだけ
-
味の再現性が高く、教育しなくても一定品質が提供できる
仕込みの負担を減らせるため、新店が増え、ラーメンが全国で均質化する流れが加速しました。
「とんこつ」とメニューに書いてあっても、昔ほど店ごとの差が出ないのは、こうした背景があるからです。
コンビニの冷凍ラーメンは美味しくなっている
ここで難しいのは、均質化=劣化 ではないことです。
実際、私はとんこつよりも 鶏白湯 や 泡系のクリーミーなラーメン を好みますが、
大阪には本当に美味しい店が多いと感じています。
そして驚くべきは、コンビニの冷凍ラーメンのレベルの高さ です。
-
セブンのとみ田系つけ麺
-
ローソンの鶏白湯
-
ファミマ×有名店コラボ
これらは下手なラーメン屋を普通に超えていて、「家で良くない?」 と思わせるレベルに達しています。
ラーメン業界は二極化へ向かう
今後、ラーメンは次の二極にハッキリ分かれていくと考えています。
| 方向性 | 特徴 | 例えるなら |
|---|---|---|
| 尖った個性・ブランド特化 | 炊き方、香り、麺、ストーリー、店主の哲学 | 「目的地として行く店」 |
| 手軽さ・アクセス性重視 | 立地、価格、速さ、安定した味 | 「日常の外食の選択肢の一つ」 |
つまり、
「特別に食べに行くラーメン」 と 「ただ空腹を満たすためのラーメン」 に分かれていくということです。
そして、どちらか片方に振り切れない店は、埋もれていく可能性が高まります。
では、これからのラーメンに何を求めるのか
私自身は「香りの記憶」が残るラーメンが好きです。
-
鶏の甘い香り
-
出汁の蒸気が鼻を抜ける瞬間
-
丼を置かれたときの期待感
これは、工場生産では再現が難しい「店でしか味わえない体験」です。
ラーメンは料理であると同時に、
空気の味わいであり、店の気配の体験 なのだと思います。



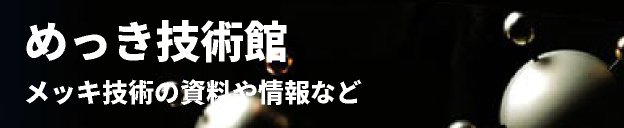
コメントを残す