ブログ
米には七人の神様がいる。そして、今、七人の“悪神”が現れた。
米の価格が高騰し、「米騒動」という言葉がSNSなどで聞かれるようになりました。
気になって調べてみると、普段は見過ごしてしまう構造的な問題が、こうした非常時に浮かび上がってくることがよくわかります。
今回は、大正・平成・令和と続く「米騒動」を比較しながら、現代の状況とその背景について、自分なりにまとめてみたいと思います。
■ 大正・平成・令和、それぞれの「米騒動」
● 大正の米騒動(1918年)
シベリア出兵を見越した米の買い占めと、それによる価格高騰。
市民の怒りが爆発し、各地で暴動が発生。最終的には寺内内閣が総辞職し、民主主義的な改革=大正デモクラシーへと繋がりました。
● 平成の米騒動(1993年)
冷夏による大不作で米の店頭在庫が消失し、パニック買いが発生。
外国産米(タイ米など)の緊急輸入が行われ、備蓄米制度の整備が進められるきっかけとなりました。
● 令和の米騒動(現在進行形)
長年続いた減反政策で、米の供給体制が硬直化。
そこに猛暑による不作と、インバウンド需要の急増が重なり、需給バランスが崩壊。
備蓄米21万トンの放出が決定されたものの、流通されない米、キロ4,000円超の価格、そして犯人探しがSNSを中心に始まっています。
■ JAだけが悪いのか?
SNS上では「JAが出し渋っている」「買い占めている」といった批判が目立ちます。
しかし、これは誰か一人が悪いというより、それぞれのプレイヤーが自分たちの利益を最大化しようと動いた結果、全体として機能不全を起こしているとも言えるでしょう。
-
JAは農家から米を買い取り流通させる仕組みを担ってきましたが、その力は年々弱まっています。
-
農家は生活のため、直接契約やEC販売など、JAを通さない販売方法を模索するようになっています。
-
外食チェーンは供給確保のため、年単位での契約を行い、自社の安定供給を最優先しています。
-
国が備蓄米を放出する決断をしたのは、価格高騰という“災害ではない理由”としては異例のことです。
このように、それぞれの合理的な行動の積み重ねが、結果的に社会全体の不安定さを招いています。
■ 米の価値をどう捉えるか
「米がなければ粟や稗を食べればいい」という時代から比べれば、飽食の現代においては米の価格が上がった程度で備蓄米を放出する必要があるのか、という疑問の声もあります。
一方で、メルカリなどでの転売も報告され、新規プレイヤーが“投機対象”として米を扱う動きも見られます。
食料という「ライフライン」に対して、利潤追求が優先される社会構造が生み出した混乱。それが、今回の令和の米騒動の本質ではないでしょうか。
■ 米一粒に宿る「七人の神様」
日本では昔から、米一粒に「七人の神様が宿る」と言われています。
水、土、風、虫、太陽、雲、そして作り手。
それぞれが支え合って、初めて一粒の米が実ります。
しかし今回、私はこう思いました。
米を冒涜する「七悪神」が、今の混乱を象徴しているのではないかと。
■ 現代に現れた「米の七悪神」
-
欲(よく)
米を「金」に変えることしか考えない、利益至上主義。 -
偽(いつわり)
産地や品質を偽り、消費者と生産者を欺く者。 -
疎(うとんじ)
米作りの苦労や文化を軽視し、ただの商品としか見ない視点。 -
搾(しぼり)
農家に正当な対価を払わず、流通の中間で利益を吸い上げる存在。 -
貪(むさぼり)
買い占め・転売により、市場の混乱を生む欲望の化身。 -
傲(おごり)
「自分が流通を回している」と思い込み、現場の苦労を忘れる者。 -
斥(しりぞけ)
日本の風土や文化を否定し、輸入と効率だけを追い求める者。
■ 最後に
米は、ただの食材ではありません。
それは日本の風土、文化、そして人々の営みと深く結びついた「魂の食べ物」です。
令和の米騒動が、ただの一過性の事件として片付けられるのではなく、日本の農業政策、食文化、そして流通構造を見直す契機となることを願ってやみません。



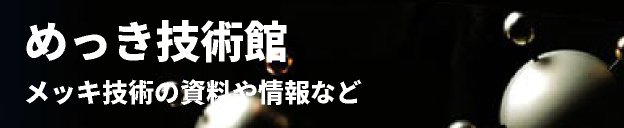
コメントを残す